二次会 買取・下取もお任せください!

- 【中古】デジタルカメラ
- 【中古】フィルムカメラ
- 【中古】レンズ
- 【中古】カメラアクセサリー
- 【中古】光学機器
- 【中古】バッグ
- 【中古】鉄道模型
- 【中古】筆記具
- 【中古】三脚
- 【中古】その他
- 【買取】買取カテゴリー
- 【新品】デジタルカメラ
- 【新品】フィルムカメラ
- 【新品】レンズ
- 【新品】カメラアクセサリー
- 【新品】フィルム
- 【新品】レンズアクセサリー
- 【新品】光学機器
- 【新品】バッグ
- 【新品】プロ機材
- 【新品】メモリーカード
- 【新品】写真整理用品
- 【新品】防湿庫・メンテナンス用品
- 【新品】周辺機器
- 【新品】筆記具
- 【新品】三脚
- 【新品】その他
- リセット
【中古】カメラアクセサリー

【買取】デジタルカメラ
【買取】フィルムカメラ
【買取】レンズ
【買取】その他カメラ関連商品
【新品】カメラアクセサリー
- 【新品】バッテリー
- 【新品】ストラップ
- 【新品】ファインダー
- 【新品】グリップ
- 【新品】ボディキャップ
- 【新品】カメラケース
- 【新品】スクリーン
- 【新品】レリーズ・リモコン
- 【新品】露出計
- 【新品】アウトドアグッズ
- 【新品】ストロボ
- 【新品】ストロボ用品
- 【新品】水中ハウジング
- 【新品】その他カメラアクセサリー
- 【新品】電池

【新品】三脚
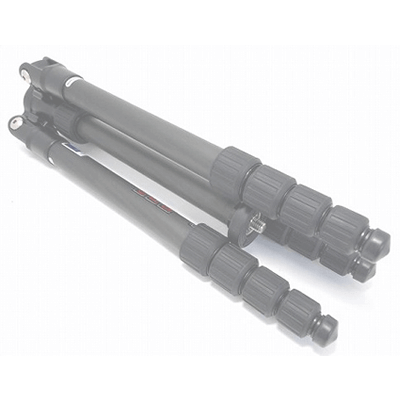
閲覧履歴
最近見た商品がありません。
履歴を残す場合は、"履歴を残す"をクリックしてください。
偽サイトにご注意下さい
当社が運営しているオンラインショップ・WEBサイトから画像や商品情報を無断で使用している「偽サイト」が発見されました。
URLをご確認下さい。
正しいURLは = https://cameranonaniwa.jp/shop/〜

このサイトはグローバルサインにより認証されています。SSL対応ページからの情報送信は暗号化により保護されます。
カテゴリから探す
<古物商許可番号> 第621110801062号 大阪府公安委員会 株式会社 ナニワ商会
Copyright © 2015カメラ買取 / レンズ買取
/中古カメラ販売・買取 NANIWA Group All Rights Reserved.<適格請求発行事業者登録番号>T4120001086246









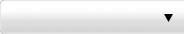
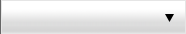
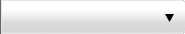



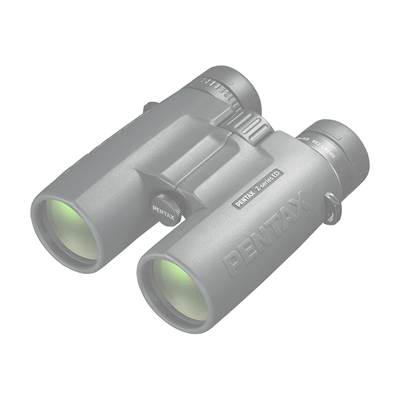

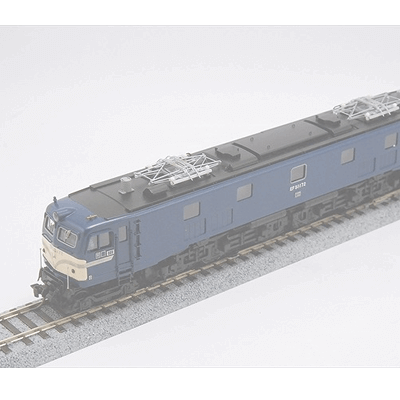


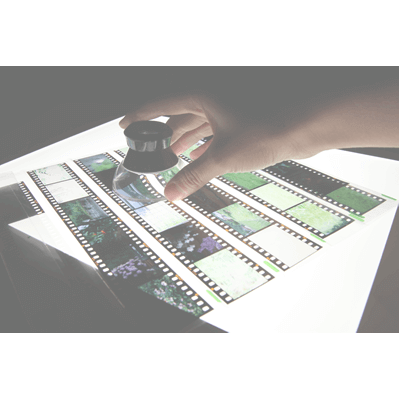

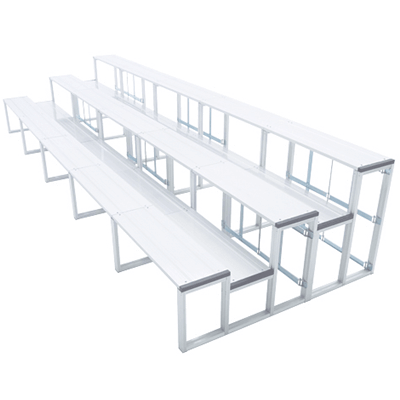



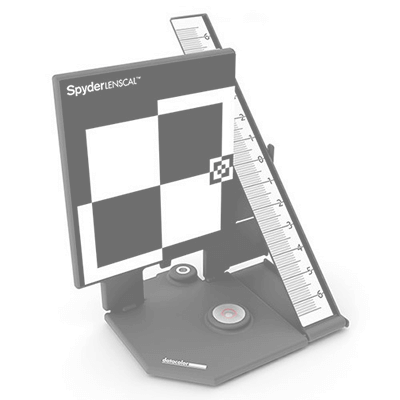





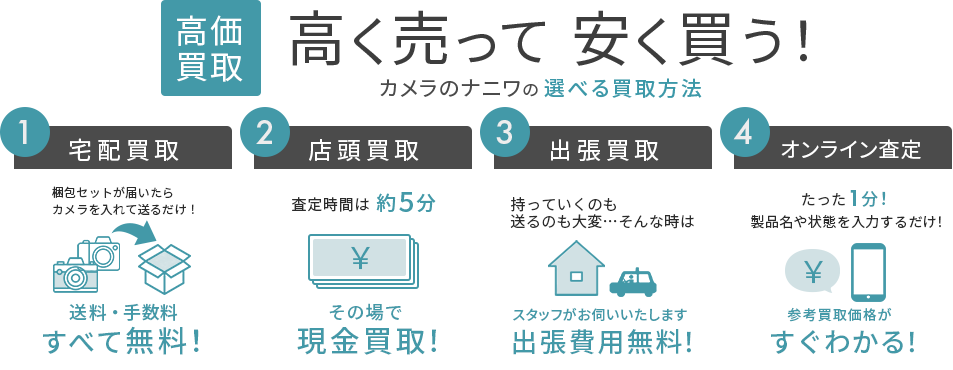
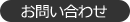
![[ 受付時間 ] 平日 10:00〜18:00※土・日・祝日も対応](/img/usr/footer/open_time-wt.png)

