新着!おすすめ中古入荷情報<<一覧はココをクリック>>
どんどん値下げ おすすめ中古品<<一覧はココをクリック>>



Billingham 【中古】(ビリンガム) Billingham 25 リュックサック カーキキャンバス x タンレザー
在庫有り
値下げしました
¥74,800
¥71,000
2221000129616



Peak Design 【中古】(ピークデザイン) ピークデザイン エブリデイスリング6L ミッドナイト BEDS-6-MN-2
SOLD OUT:販売を終了しました
値下げしました
¥10,200
¥9,600
2221150096394



Canon 【中古】(キヤノン) Canon EOS 5D MARK III + EF24-105/4L IS USM
在庫有り
値下げしました
¥140,000
¥126,000
2111012408192
話題の新製品!!<<一覧はココをクリック>>
【新品】3年間延長保証付対象商品
ナニワグループのINSTAGRAM
トピック
- 2024/05/02 本日の♪どんどん値下げ♪通販オススメお買い得の中古カメラ・中古レンズを『16点』追加掲載しました!!
- 2024/05/01 本日の♪どんどん値下げ♪通販オススメお買い得の中古カメラ・中古レンズを『168点』追加掲載しました!!
- 2024/04/30 本日の♪どんどん値下げ♪通販オススメお買い得の中古カメラ・中古レンズを『107点』追加掲載しました!!
- 2024/04/29 本日の♪どんどん値下げ♪通販オススメお買い得の中古カメラ・中古レンズを『67点』追加掲載しました!!
- 2024/04/28 本日の♪どんどん値下げ♪通販オススメお買い得の中古カメラ・中古レンズを『30点』追加掲載しました!!
- 2024/04/27 本日の♪どんどん値下げ♪通販オススメお買い得の中古カメラ・中古レンズを『38点』追加掲載しました!!
- 2024/04/26 本日の♪どんどん値下げ♪通販オススメお買い得の中古カメラ・中古レンズを『164点』追加掲載しました!!
- 2024/04/25 本日の♪どんどん値下げ♪通販オススメお買い得の中古カメラ・中古レンズを『106点』追加掲載しました!!
- 2024/04/24 本日の♪どんどん値下げ♪通販オススメお買い得の中古カメラ・中古レンズを『278点』追加掲載しました!!
- 2024/04/23 本日の♪どんどん値下げ♪通販オススメお買い得の中古カメラ・中古レンズを『384点』追加掲載しました!!









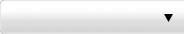
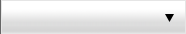
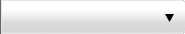





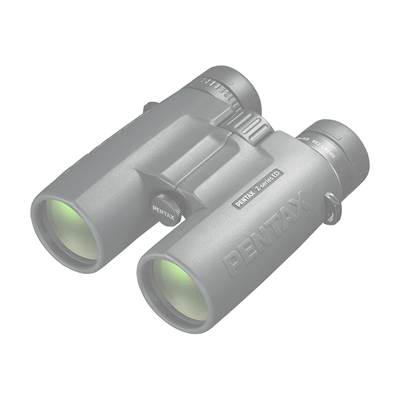

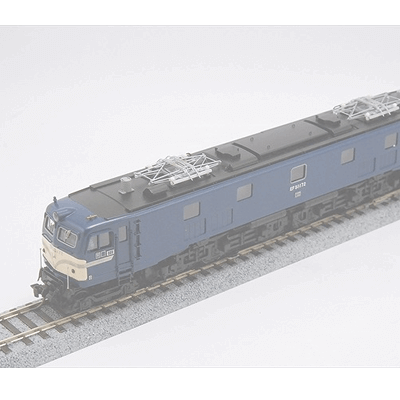

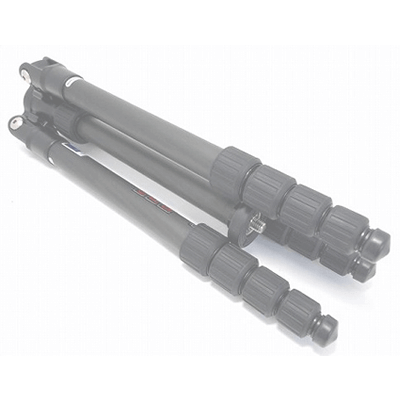

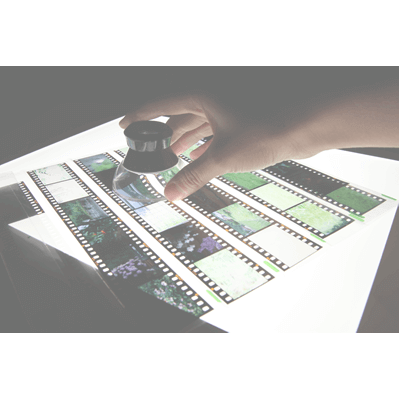

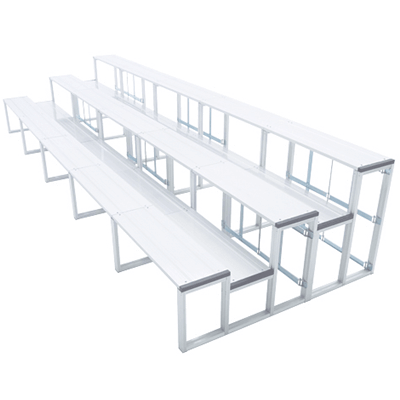



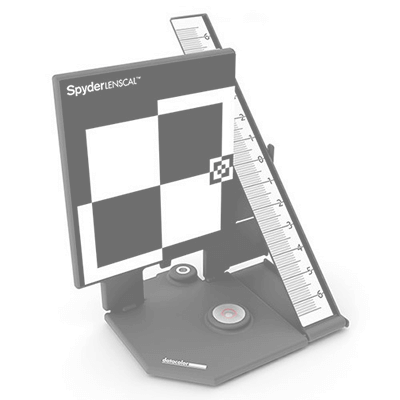


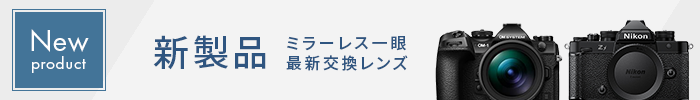
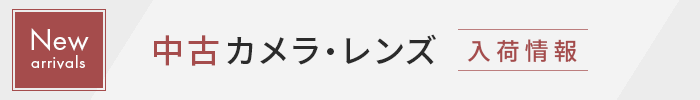
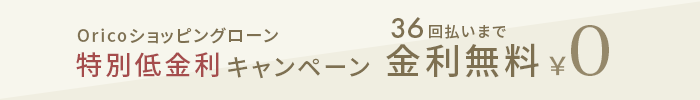




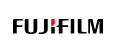
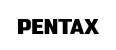











































































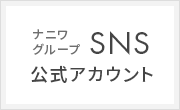
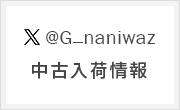
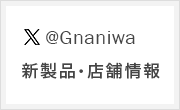




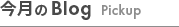



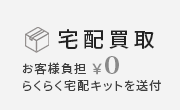
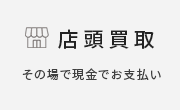
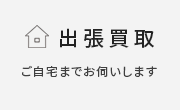
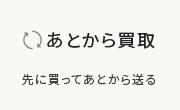
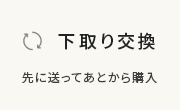
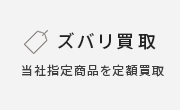
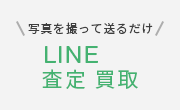
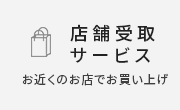




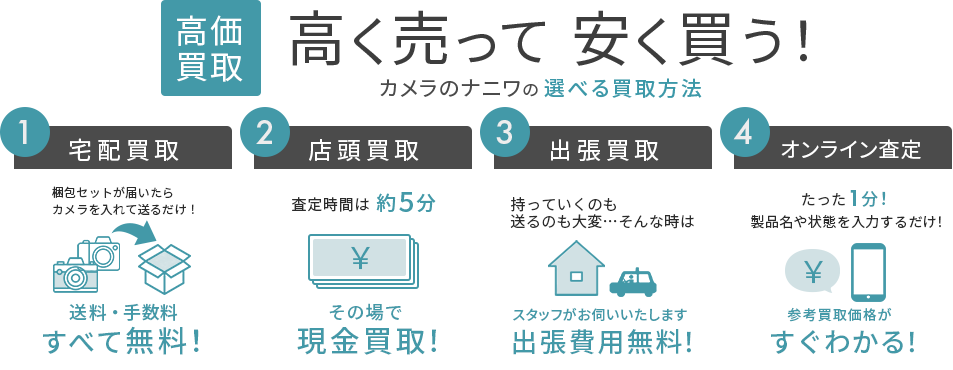
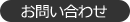
![[ 受付時間 ] 平日 10:00〜18:00※土・日・祝日も対応](/img/usr/footer/open_time-wt.png)

